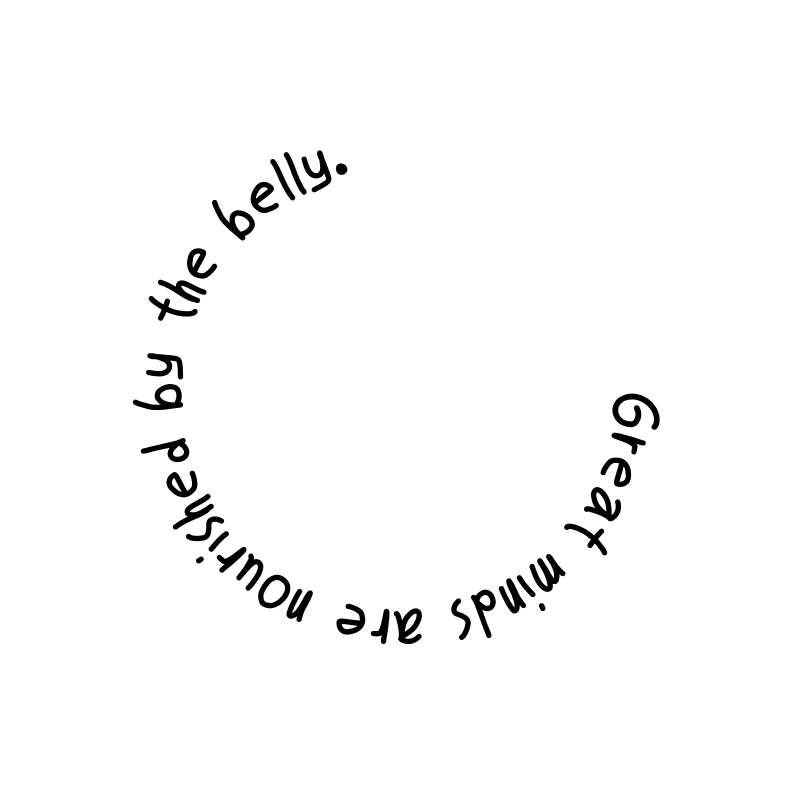犬の食物アレルギーの概要
犬の食物アレルギーは、特定の食物やその成分(主にタンパク質)に対して免疫系が過剰に反応し、炎症を引き起こす状態です。猫と同様に、皮膚疾患や消化器症状として現れますが、皮膚症状が最も多く見られるという特徴があります。
疫学と好発品種
過去の調査では、皮膚疾患を持つ犬の**約10%**が食物アレルギーに関連していると報告されており、猫に比べて報告例が多いとされています。
- 特定の品種(例:ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバーなど)で好発する傾向があるという報告もあります。
- どの年齢でも発症する可能性がありますが、若い年齢での発症も多く見られます。
主な症状
犬の食物アレルギーでは、皮膚症状が最も一般的に見られ、消化器症状が単独で現れるケースは約20〜30%とされています。
皮膚症状
- かゆみ(痒疹、掻痒):特に耳、顔面、足先、肛門周辺に現れやすいです。季節に関係なく一年中続くことが多いのが特徴です。
- 皮膚炎:皮膚の赤み、発疹、フケ、かさぶたなどが見られます。
- 外傷性脱毛症:掻いたり、舐めたり、噛んだりすることで引き起こされます。
- 繰り返す外耳炎:食物アレルギーが原因で慢性的な外耳炎を発症することもあります。
- 二次感染:患部を掻き壊すことによって、細菌や真菌(マラセチアなど)による二次感染を併発することがよくあります。
消化器症状
- 嘔吐、下痢、軟便、排便回数の増加、おなら(ガス)がたまるなどの症状が見られます。皮膚症状と合併して現れることが多いです。
アレルゲンとなる主な食物
犬の食物アレルギーの主なアレルゲンとしては、以下のものが多く報告されています。
- 牛肉
- 乳製品
- 鶏肉
- 小麦
- 大豆
タンパク質や一部の炭水化物などが原因となることが多く、犬が生涯を通して食べてきたフードに含まれる成分でも、アレルギーを発症する可能性があります。
診断方法
食物アレルギーの診断は、獣医師の指導のもとで行われる**「除去食試験」**が最も信頼性の高い方法とされています。
- 除去食試験:通常8〜12週間以上にわたって、今まで食べたことのない新しいタンパク質源(低刺激性)、または加水分解されたタンパク質を含む専用の食事(療法食)を与え、水以外のものは一切与えない生活を送ります。
- 症状が改善(約80%の犬で改善が報告されています)すれば、食物アレルギーの可能性が高いと判断されます。
- 負荷試験(誘発試験):除去食試験で症状が改善した後、アレルゲンと疑われる元の食事や単一の食物を再び与え、症状が再発することで確定診断となります。
- 血液検査や皮膚テストは、食物アレルゲンのリストアップや補助的な手段として行われることがありますが、診断においては除去食試験が基本となります。
治療と管理
食物アレルギーの治療は、原因となるアレルゲンを特定し、それを食事から完全に除去する食事管理が中心となります。
- アレルゲンの回避と除去食の継続:除去食試験で症状が改善した食事を生涯継続することが、基本的な治療となります。
- アレルギー専用フードの選択:低アレルゲンとされる単一タンパク質のフード、加水分解タンパク質フード、またはグレインフリー(穀物不使用)のフードなどが選択肢となります。
- 対症療法:かゆみや炎症、消化器症状がひどい場合は、投薬(例:抗ヒスタミン薬、ステロイド、免疫抑制剤など)によって症状を緩和する治療を併用することもあります。
- 二次感染の治療:細菌や真菌の二次感染が起きている場合は、抗生剤や抗真菌薬などによる治療を行います。
犬の食物アレルギーは適切な食事管理によって良好な予後が期待できますが、生涯にわたる管理が必要となります。