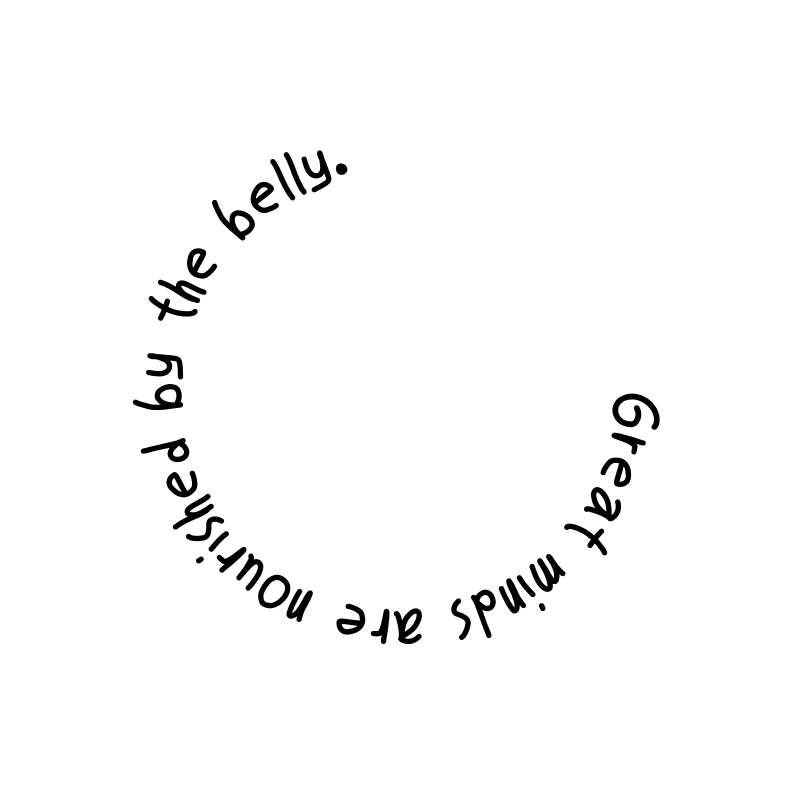なぜ国によって規制が違うのか?
このような違いが生じる主な理由は以下の通りです。
- リスク評価の手法と基準: 各国・地域の食品安全機関(例: 日本の食品安全委員会、EUのEFSA、アメリカのFDA)が、科学的データに基づいてリスク評価を行います。その評価基準や、リスクと便益のバランスの考え方に違いがあるためです。
- 予防原則の考え方: EUは、少しでも安全性が疑われる場合は使用を禁止するという「予防原則」の考え方を強く採用する傾向があります。一方、日本やアメリカは、科学的に明確なリスクが確認されない限りは使用を許可するという姿勢が比較的強いとされています。
- 国民の意識と食文化: 各国の消費者が食品添加物に対して抱くイメージや、伝統的な食文化も規制に影響を与えることがあります。
- 産業界の要望: 食品産業界からの要望やロビー活動も、規制の策定に影響を与えることがあります。
消費者は、これらの情報を踏まえ、自身の判断で食品を選択することが重要です。特に、海外からの輸入品を購入する際は、現地の規制と日本の規制が異なる可能性があることを念頭に置くと良いでしょう。
合成甘味料(アスパルテーム、アセスルファムKなど)
ゼロカロリー飲料などに使われ、動物実験で発がん性が指摘されたり、WHOがアスパルテームを発がん性が疑われる物質に分類したりしています。腸内環境の悪化やインスリン抵抗性のリスクも示唆されています。
サッカリン(合成甘味料)
- 禁止国: かつてアメリカでは発がん性の懸念から使用禁止とされていましたが、現在は撤回され、警告表示を条件に利用されています。一部の国では未だ使用が禁止されている場合もあります。
- 日本での状況: 戦後、安価な甘味料として広く使われましたが、発がん性の懸念からチクロ(別の甘味料)とともに使用が制限・禁止されました。現在はごく一部の食品に限り使用が認められています。
合成着色料(赤色102号、黄色5号など)
合成着色料は、鮮やかな色合いを出すために多くの加工食品に使用されていますが、一部は健康への影響が懸念され、海外で規制されているものがあります。
菓子や飲料などに使用され、発がん性やアレルギー症状のリスク、小児の行動障害(ADHD)の原因となる可能性が指摘されており、一部の国では使用が禁止されている場合もあります。
赤色2号(タール色素)
- 禁止国: アメリカ、カナダ、ノルウェーなど。特にアメリカでは発がん性の可能性が指摘され、1976年に使用が禁止されました。
- 日本での状況: 日本では、清涼飲料水、菓子類、氷菓などに使用が認められています。
赤色102号(タール色素)
- 禁止国: アメリカ、カナダなど。
- 日本での状況: 日本では、菓子、清涼飲料水、漬物などに使用が認められています。
黄色4号(タートラジン)
- 禁止国: ノルウェーなど一部の国。また、EUでは表示義務があり、子供の行動に影響を与える可能性が示唆されています。アラブ首長国連邦では輸入禁止措置が取られています。
- 日本での状況: 日本では広く使用されています。
クチナシ色素(一部)
- 禁止国: アメリカやEUでは、クチナシ色素の一部(赤・青・黄の3種類すべて)が食品添加物としての使用が禁止されています。
- 日本での状況: 日本では「クチナシ色素」として一括表示され、使用が認められています。
アミノ酸系調味料
グルタミン酸ナトリウム(MSG)
最も代表的なうま味調味料で、昆布のうま味成分です。前述の通り、国際機関も安全性を確認していますが、一部で「中華料理店症候群」と呼ばれる頭痛やしびれなどの症状が報告されることがあります。これは過剰摂取や個人の体質によると考えられています。また、高濃度のグルタミン酸摂取と神経変性疾患の関連を示唆する研究もありますが、通常の食事量での影響は否定的です。
L-アスパラギン酸ナトリウム
アスパラガスや肉などに含まれるアミノ酸のアスパラギン酸のナトリウム塩です。グルタミン酸と同様に、特定の条件で神経細胞への影響が指摘されることがありますが、一般的な食品添加物としての使用量では安全性は確認されています。
核酸系調味料
核酸系調味料は、グルタミン酸と組み合わせることで相乗効果を発揮し、より強いうま味を感じさせるとされています。安全性については、一般的に食品添加物として使用される量であれば問題ないとされていますが、核酸の代謝産物である「プリン体」の過剰摂取は、痛風のリスクを高める可能性が指摘されています。ただし、調味料として使用される量は微量であり、通常の食事で痛風のリスクが高まるほど摂取することはないと考えられています。ナトリウムを含むため、塩分摂取制限が必要な人は注意が必要です。
イノシン酸ナトリウム
カツオ節や肉のうま味成分であるイノシン酸のナトリウム塩です。
グアニル酸ナトリウム
干ししいたけのうま味成分であるグアニル酸のナトリウム塩です。
臭素酸カリウム(パン生地改良剤)
- 禁止国: EU(1994年)、英国(1990年)、カナダ、ブラジル、中国(2005年)など多くの国で禁止されています。発がん性の可能性が指摘されています。
- 日本での状況: かつては広く使用されていましたが、発がん性の懸念から一時使用が自粛されました。現在は、最終食品に残存しないことを条件に一部のパンに限り使用が認められています。しかし、日本の大手パンメーカーの多くは自主的に使用を中止しています。
- 米国での状況: 米国では使用が認められていますが、カリフォルニア州では警告ラベルの表示が義務付けられています。
発色剤、保存料
亜硝酸ナトリウム
- 禁止・制限国: EUやアメリカでも使用は認められていますが、摂取量や使用対象に厳しい基準が設けられています。特に、肉中のアミンと結合して発がん性物質であるニトロソアミンを生成する可能性が指摘されています。
- 日本での状況: ハム、ソーセージなどの加工肉や魚卵(いくら、たらこなど)に広く使用されています。
ゾルビン酸カリウム
各国の食品安全機関(日本の厚生労働省や食品安全委員会、欧州食品安全機関(EFSA)、アメリカ食品医薬品局(FDA)など)は、ソルビン酸カリウムの安全性評価を行っており、定められた使用基準(一日摂取許容量 ADI)の範囲内であれば、単独での使用はもちろん、亜硝酸ナトリウムとの併用においても安全性は確保されていると結論づけています。体内で反応が起こる可能性は否定できないものの、実際の食品に含まれる濃度や摂取量では、リスクは極めて低いとされています。